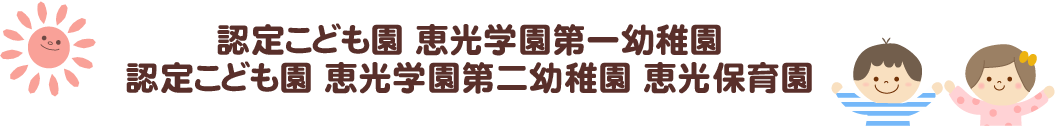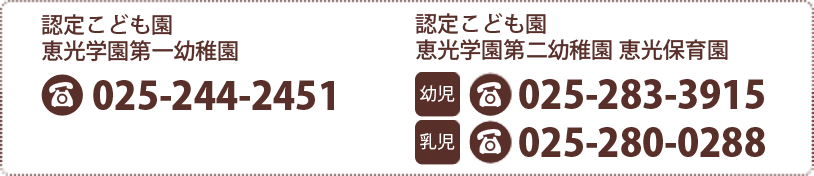今月の園だより
10月の主題
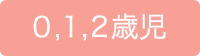
- うごく

- 動く
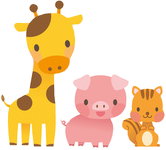
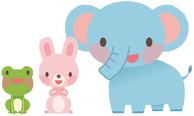
ねらい
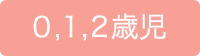
- 0歳児 ・保育者と一緒にさんびかを歌う
- ・戸外で気持ち良く遊ぶ
- ・身近にいる保育者や子どもの真似をしたり試してみたりする
- 1・2歳児・見えない神さまの存在を感じ、共に礼拝する
- ・リズムに合わせて体を動かすことを喜ぶ
- ・秋の自然の中でのびのびと外遊びを楽しむ

- ・神さまのくださっている力と知恵を合わせて共に過ごす
- ・生活や遊びの中で、自分の気持ちや考えを表現し、友だちや保育者と伝え合う喜びを味わう
- ・いろいろな遊びのなかで、体を十分に動かして楽しむ
- ・気候の変化を体で感じながら、衣服の着脱や休息の調整をしようとする
10月の聖句
アブラムは、主の言葉に従って旅立った
創世記12章4節
10月の讃美歌
わたくしたちは
こども讃美歌
先日、第1園の改築に伴っての園庭整備計画の為「乳児期の為の外遊びの重要性」という講演会(「森のようちえん」全国ネットワーク代表の方のお話)を夜、長岡の設計士さんと一緒に聴きにいってきました。 講師は長野県の幼稚園の方なので、この夏は川遊びをほとんど毎日のようにしていたとのこと。泳げることが目標ではないけれどみんな川で泳ぐことを、その子なりに習得していき、川の危なさも学んでいくとのことでした。
「自然は環境設定をわざわざしなくても、十二分に子どもが発達する保育環境がなされている」という言葉には本当にそうだなーとあらためて思いました。我が家は駐車場が裏手にあるので、いつも雑草のような小路を通っていくのですが、毎朝、その途中に必ず蜘蛛が蜘蛛の巣を張りたくさんの小さい虫を生け捕りにしています。人間様が通る為に「ごめんね」と言いながらそれを壊さざるを得ないのですがこれがよくみると面白いのです。蜘蛛の巣は雨上がりだとキラキラ光ってその中に黒と黄色のまだらの大きい蜘蛛がえばって陣取っているさまが思わず写真を撮ってしまう位凄いのです。先日孫がその光景をみて「こわ~いムシがいる~!」と叫びました。偶然訪れた環境についていけなかったのでしょう。
「これからの日本の子はどんな状況になってもそれを切り開いていける力を作る子でないと、伸びていけない」と講師の先生が言っておられました。都会の真ん中にある第1園の園庭がそういう力を培う園庭になれるよう試行錯誤していこうと思います。(第1園は狭い土地なので屋上に園庭を作ります。土を使い、緑も取り入れたものを工夫していこうと設計士さんと話し合っています。)
今「安全運転管理者講習」という法定講習を受けながら休み時間のたびにこれを書いています。その講習会の中でこれは大事!ということを皆さんにもお伝えしようと思います。
①日没前後1時間が事故が最も多い。早めにライトを点灯して、いつもより気を付ける。
②交差点ではしっかり予測しながら走る(右折では直進車ばかりに気が回り横断歩道での歩行者や自転車の通行に不注意になりが ち)(駐車場もこの交差点走行位危ないとのことです。第1園のお母様方、駐車場を横切るのはとても危ないです)
③横見運転の事故は事故原因の73%だそうです。スマホ見ながら運転は厳禁とのこと。
(以前第2園で、「鳥屋野中学近くの私道に近い道路を速度を落とさずに朝、園に向かって行った園児さんの車をみましたので注意してください」と近所の方からクレームがありました。狭い道走行は交差点走行と同じ位注意が必要でしょう。気を付けましょう!)
大の大人が200人ほどぎっしりと大会議室に詰められてのカンヅメ講習会でしたが、なかなか身震いのする話が警察関係の方から聞くことが出来、身の引き締まる思いのけいこ先生でした。