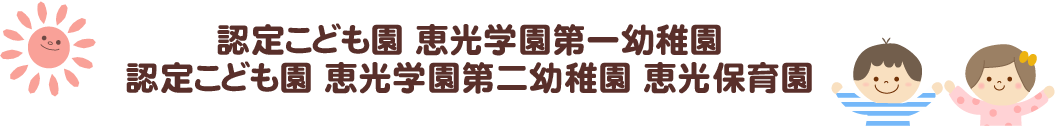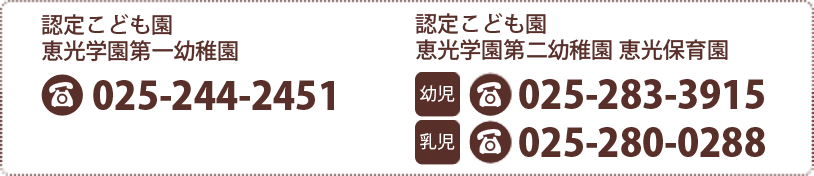今月の園だより
3月の主題
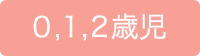
- おおきくなった

- おおきくなった
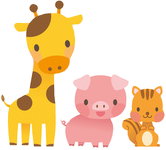
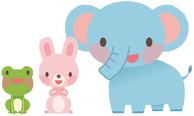
ねらい
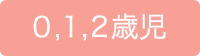
- 保育者や友達と共に喜んで礼拝を守る
- 自分でやりたいという思いをもつ
- 家庭や保育者間の丁寧な連携の中で安心して進級する

- 新しい生活へ安心して向かおうとする
- 友だちと協力し。アイデアを出し合い、工夫して遊びを充実させる
- お互いが、かけがえのない存在であることを感じ、感謝して過ごす
- 助けあうことを大切に思い、祈る
3月の聖句
義の実は、平和を実現する人たちによって、平和のうちに蒔かれるのです
ヤコブの手紙3章18節
3月の讃美歌
つくしのように
先月の研修会で先生方が絵本の研修を受けてきました。
その時「面白かったです」という「ねこのピート」という絵本(エリック・リトウイン作)の訳者大友剛さんの弾き語りの講演でなおかつマジシャンでもあるので、いろんな楽しい学びをしてきたとのこと。 私も2冊、さっそく先生方からかりて、2歳ちょっとの子どもに読んで聞かせてみました。 一緒によみながら、何回か読んでいると、もう、すぐに最後の繰り返しの歌は2歳児なりのイントネーションで何気なくちょっとした時に歌っているのです。
そして、次の日に「はっぱの書いている本読んで~」とおねだりされました。 一緒に読んだ大友さんの訳書「ふしぎなふしぎなまほうの木」のことでした。 こんなに2歳の子どもでも、絵本の楽しさが伝わり心に沁みわたっているのだなあと感動してしまいました。
こぐま社の吉井康文さんが「ことばの力、絵を読む力」という文の中で次のように書いておられます。
【絵本は元々、文字が読めない、読めてもその理解が十分でない子どもの為に、絵という文字の助けを借りて作られたものです。文字の読めない子どもは、お話しを耳で聞いて絵という文字を読んで絵本を読んでいきます。この絵を読む力がすごいのです。・・・主人公にもなれるし、主人公の友達にも自由になれるのです。その中で一緒にうれしくなったり、悲しくなったり、ハラハラドキドキを経験して、心を動かしています。人の気持ちも痛みもわかるのです。子どもは想像力、創造力、記憶力など様々な力を駆使して絵本を読みます。そうして,ことばの力も育まれていきます。・・・】
そうなんですね。心が動いているのですね。
≪お母さんの声を耳で聞きながら、目で絵をよみながら、心をたくさん働かしているんですね≫
吉井さんはまた次のようにも警鐘をならしています。
「愛情のこもった肉声で、人格のあることばで、まだことばの意味もわからない赤ちゃんに語りかけています。赤ちゃんは全身でそのことばを聞いています。そのことがある時期になって話す力、読む力、書く力、理解する力、などのことばの力になっていくのに、現在その手段が確実に減ってきているのを感じるそうです。スマホで買い物をしながら赤ちゃんに授乳、その横で子どもがテレビゲームをしているという光景もありがちです・・・」
そうなんですね。 片手間に出来るので、ついつい「ながら技」をやってしまうのですね。
でもそれはやはり「人格のある肉声」にはなっていないかもしれませんね。 今度是非、絵本を読み聞かせしながら「人格ある肉声」がたくさん聞かせられているか、「ながら技」をたくさん使っていないか等、振り返ってみるのもいいかもしれませんね。