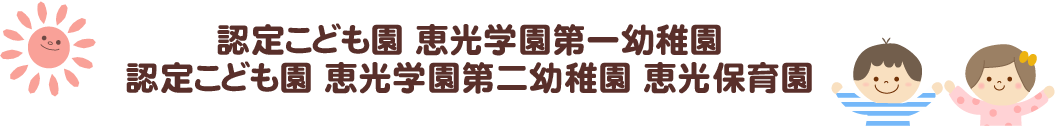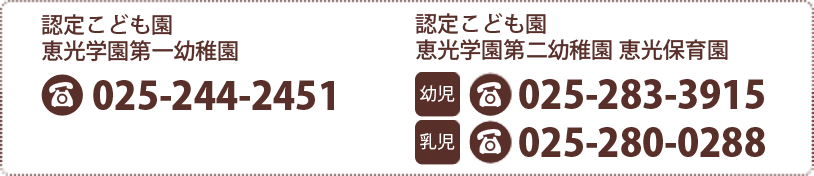今月の園だより
4月の主題
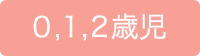
- であう

- 出会う
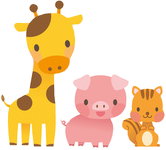
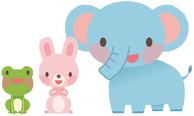
ねらい
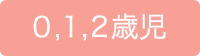
- 0歳児のねがい ・保育者は神さまから与えられた出会いを喜ぶ
- ・新しい環境や保育者に出会う
- ・保育者に守られて安心して過ごす
- 1・2歳児のねがい ・保育者の祈りを通して神さまと出会う
- ・新しいj環境や保育者に親しみを感じる
- ・保育者に守られて安心して過ごす

- ねがい ・祈りを通して神さまと出会う
- ・保育者にあたたかく受け入れられ、安心して過ごす
- ・保育者と保護者が信頼関係を築く
4月の聖句
あなたがたに平和があるように
ヨハネによる福音書20章19節
4月の讃美歌
空の鳥は
こども讃美歌
ご入園、ご進級おめでとうございます。
子ども達だけでなく、お母様方の中にも、幼稚園、認定こども園に初めて預ける方もおられることと思います。「幼稚園ママ、認定こども園ママ」1年生として、先輩ママさんからいろいろ学びつつ成長していきましょう!
さて、「こどもは遊びを通して学んでいく」と私たちはいつも言っていますが、勉強的なことも必要ではありませんか?等々きかれることがあります。
「遊びの本質とは?」という特集で4月号の「母の友」で特集がありました。そうそうそうなのよ!という事柄がたくさん書かれていましたので、抜粋してみます。
「遊びの本質は『自由』だと思います。道端の棒切れなど遊び道具ではないものを使って、自分で好き勝手に考えた遊びをしますが決められた枠から外れていくところにこそ面白さがあり、だからこそクリエィティビティー(創造性)が養われる。」・・・これは「かくれんぼができない子どもたち」を書いた杉本厚夫さんのコメントです。
そして白梅学園大学学長の汐見稔幸先生は「子どもは大人に『遊びなさい』と指示されなくても、自発的に走ったり、描いたり、踊ったり、いろいろなことをして遊びますよね。なぜでしょうか。『楽しいから』ですよね。集団で遊ぶ時も同様です。みんなでいると楽しいから集う。でも楽しさを生み出す、あるいはキープするのは意外と大変です。楽しさのためにこどもは必死で知恵を絞る。今日は何をして遊ぼうかな。一日を楽しいままで終わらせるのは至難の業です。途中でケンカになったりすることもある。そして失敗も大事な経験です。それは『どうしてこうなっちゃったのかな』と考えることにつながる。そして次はこうしてみようかな、と思う。このように遊びの中では『自分で考える』『工夫する』という行為が生まれます。・・・つまり遊びは『考える力』や『工夫する力』も育ててくれる。・・・そしてほめ過ぎ母さんになると、人の評価に敏感になりすぎてその枠から出ていけず、遊びが人の目を気にしつつの遊びになってしまう。一方がみがみ母さんだと自由な遊びが出来ずとまってしまう。というわけで子どもの遊びはあまりほめたりけなしたり評価をせず、温かく見守るのがこつです。」とのこと。「遊びに『ねばならない』はありません。子ども本人が『したい』と思ってやるのが遊びです。『したい』世界を『ねばならない』世界に変えてしまうと、それは遊びではなくなってしまいます。おもしろくおかしく遊んでいいんだよ。失敗なんて気にしないで遊びなさい、子どもはそうした雰囲気の中で遊ぶことで自分はありのままでいいんだという自己肯定感、そして試行錯誤を否定されないことで、知恵を絞ってやればなんとかなるという自己有能感を得ることができます。わかりやすい言葉でいうと『折れない心』『あきらめない力』が育まれているのです。入学前に文字が書けるとか九九が言える。というような能力を最近は認知的スキルと呼ぶがそうした「認知的スキルが高い子」が「頭がいい子」と言われることが多いように感じます。認知的スキルは人間が持つ力のほんの一部ですし、また、認知的スキルのために得た知識は将来忘れることがあります。・・・一方、遊びを通じて、自ら獲得した『考える力』や『共感力』は一生なくなることはありません。そして『折れない心』と『あきらめない力』があれ、仮にかつえ覚えたことを忘れたとしても、また調べて覚えればいいや、と思うんじゃないでしょうかね。」・・・と語られています。
認知的スキルばかりやらされて、ねばならない遊びを強いられて「よい子」になることではなく「自由で楽しいことを創りだすことの出来る人」が経済優先できた社会が変わり目を迎えようとしている現社会には必要になってくるのではないでしょうか。そういう保育をめざしたいと思います。
新年度早々ちょいと力みすぎたかな?とひそかに思っている恵子先生より
けいこせんせい